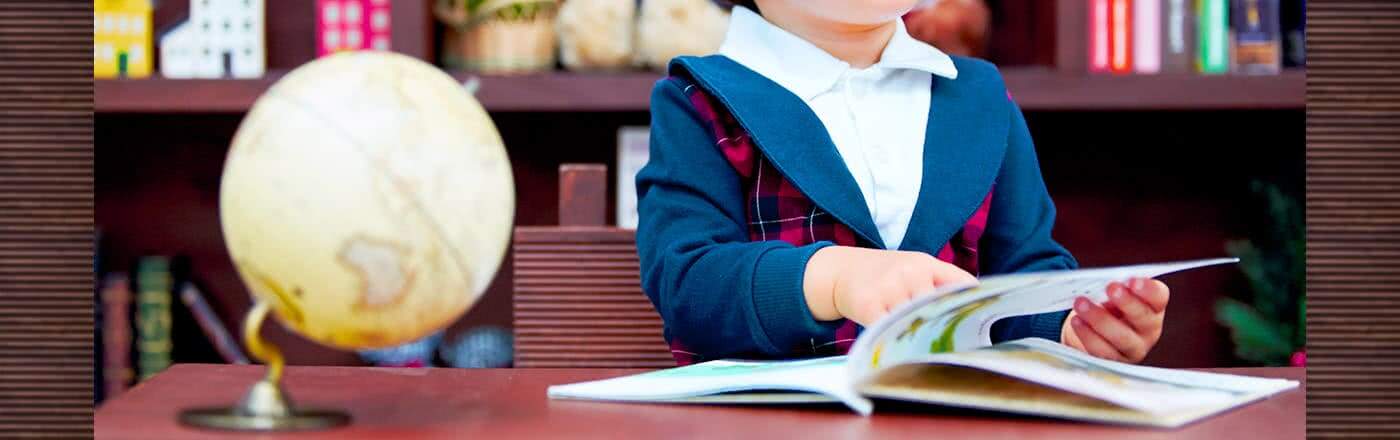法定相続情報証明制度とは?手続き・メリット・申請方法を行政書士が徹底解説
— 戸籍の束を提出する手間をなくす!相続手続きを効率化する新しい仕組み —
1.法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度は、相続に関する手続きを簡略化するために法務局が平成29年(2017年)5月29日から導入した制度です。 これまでのように、銀行・保険会社・不動産登記などの相続手続きで毎回「被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍謄本」を束で提出する必要がなくなります。
代わりに、法務局で発行される「法定相続情報一覧図」に基づき、 登記官が内容を確認・認証した「法定相続情報証明書」を提出すれば、戸籍一式の提出に代えることが可能になります。
この証明書は、銀行・保険会社・不動産登記・自動車の名義変更・年金など、 さまざまな相続手続きで利用でき、手続きの負担を大幅に軽減します。
2.従来との違いと制度のメリット
- ✔ 各手続き先ごとに戸籍一式を提出する必要がなくなる
- ✔ 法務局発行の証明書を使えば、全国どこでも利用可能
- ✔ 戸籍原本を紛失・破損するリスクを防止
- ✔ 各機関の窓口処理がスピーディーになり、手続きが簡略化
もちろん、従来通り「戸籍謄本の束」で手続きを行うことも可能ですが、 行政・金融機関側も本制度の利用を推奨しているため、今後は「法定相続情報証明書」が標準的な提出書類となりつつあります。
3.法定相続情報証明書の取得手順
① 申出(法務局への申請)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等を収集
- 法定相続情報一覧図を作成(被相続人と相続人の関係を明記)
- 上記を添付し、法務局へ申出(無料)
② 確認・交付
- 登記官が戸籍等を確認し、一覧図を保管
- 認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し(=法定相続情報証明書)」を交付
- 提出した戸籍謄本等は返却されます
③ 各種相続手続きで利用
銀行・保険・不動産・車両・年金などの手続きにおいて、 戸籍の束の代わりにこの証明書を提出できます。
4.申出できる人と代理人の範囲
- 申出できるのは、被相続人の相続人(またはその地位を承継した者)
- 遺言執行者は申出不可
- 代理人になれるのは、法定代理人のほか、次の有資格者に限られます:
弁護士/司法書士/行政書士/税理士/社会保険労務士/土地家屋調査士/弁理士/海事代理士
申出先(管轄登記所)
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産所在地
5.注意点・よくある質問
- ● 戸籍の束による従来の手続きも可能(本制度の利用は任意)
- ● 相続放棄・遺産分割協議書は別途必要
- ● 廃除された者や欠格者は一覧図に記載されない
- ● 被相続人・相続人が外国籍などで戸籍謄抄本を添付できない場合は利用不可
- ● 相続人の範囲が後に変わる場合(認知・出生・廃除など)は再申出が必要
- ● 保管期間は5年間。期間中は再交付が可能
- ● 証明書は複数通発行できる
6.法定相続情報一覧図の作成ポイント
一覧図には、被相続人と全ての法定相続人の関係を明確に記載する必要があります。 書式は法務局のサイトでダウンロードでき、手書き・パソコン作成いずれも可能です。
▶ 法務省:法定相続情報証明制度の概要・申出様式(公式サイト)
正確な作成には、戸籍の読み解きや相続人関係の整理が必要になるため、 初めての方や戸籍関係が複雑な場合は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
7.まとめ:相続手続きを効率化するなら早めの準備を
「法定相続情報証明書」を活用すれば、相続手続きに必要な戸籍提出が一度で済み、 銀行・保険・不動産などの手続きが格段にスムーズになります。
制度利用は無料で、申請から交付までの期間もおおむね数日程度です。 相続に関わる方や、将来の相続対策を考えている方は、早めに本制度を理解し準備しておくと安心です。
最新の情報や様式は、必ず法務局・法務省公式サイトをご確認ください。
執筆者:中川正明(特定行政書士/申請取次行政書士/宅地建物取引士)|福井県越前市
※本記事は法務省「法定相続情報証明制度」公式資料および各法務局案内をもとに執筆しています。