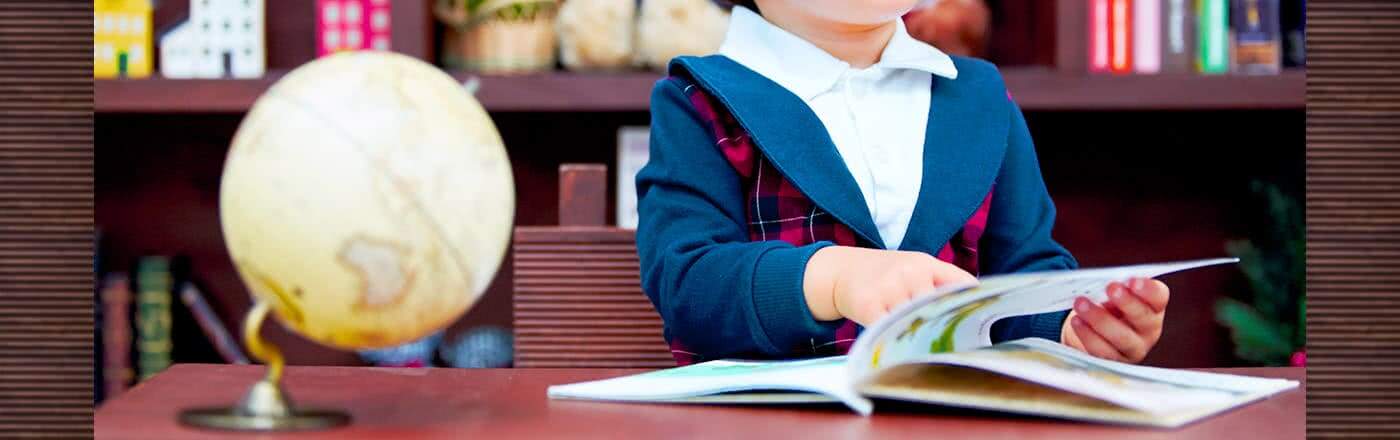遺言書で「借金」や「保証債務」はどう扱う?負の財産の相続を行政書士が解説
遺言書を作成する際、多くの方が「不動産は長男に」「預金は妻に」というように、正の財産(プラスの財産)の分配を中心に考えがちです。 しかし、相続では「借金」や「保証債務」などの負の財産(マイナスの財産)も引き継がれることを忘れてはいけません。
この記事では、借金を相続させる場合の法的な限界や注意点、そして「免責的債務引受」などの契約手法について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
1. 負の財産も「相続の対象」である
預金や不動産などの正の財産は、被相続人の所有権を相続人へ移転させることで引き継がれます。一方で、借金や保証債務などの負の財産も民法上は相続の対象です。
仮に相続人が3人(A・B・C)いたとして、被相続人が「借金をAだけに引き継がせたい」と遺言書に記したとしても、債権者(お金を貸している側)にはその遺言を拘束する力はありません。 法的には、債権者は法定相続分に基づき、A・B・C全員に返済を請求できます。
重要ポイント:
遺言書で「借金を特定の人だけに相続させる」と書いても、債権者に対しては効力を持たないのが原則です。
2. サラリーマンと経営者ではリスクの内容が異なる
◆ サラリーマンの場合
典型的なのは住宅ローンの残債です。 住宅ローン付きの不動産を「Aに相続させる」と遺言で指定したとしても、金融機関は他の相続人(B・C)にも請求できるのが原則です。 そのため、家族内であらかじめ協議し、返済方法や不動産の処理を確認しておくことが大切です。
◆ 経営者(個人事業主・法人経営者)の場合
会社の借入金に個人保証を入れているケースでは、相続人に保証債務が承継されることになります。 特に経営者の場合は、会社の財務状況・保証契約の有無・事業継承の方針などを総合的に検討し、早期に専門家へ相談することが必要です。
3. 負の財産が多い場合の選択肢
- 借金が資産を大きく上回る場合:相続放棄の検討
- 資産と負債の差が不明な場合:限定承認の検討
- 事業承継と併せて引き継ぐ場合:事業継承の専門家と連携
これらの手続きには期限(3か月以内)や書類要件があるため、迅速な判断が求められます。
4. 債権者との調整で用いられる契約:免責的債務引受と重畳的債務引受
◆ 免責的債務引受
債権者の同意を得て、「特定の相続人が債務を引き受け、他の相続人は免責される」という内容の契約を締結する方法です。 たとえば、Aだけが借入を相続し、BとCは法定相続分に応じた負担を免除されるような形です。
◆ 重畳的債務引受
債権者が同意しない場合に用いられる方式で、債務者が追加される形になります。 新たな債務者(相続人)が既存の債務者と共同して責任を負う契約形態です。
これらの契約内容を遺言書の記載内容と整合させておけば、相続開始後に慌てることなく手続きを進められます。
専門家コメント:
負の財産の取り扱いは、相続人だけでなく債権者との関係も密接です。
遺言書の記載内容を実現するには、金融機関や債権者との事前協議が不可欠です。
5. 遺言書に書けること・書けないこと
- 遺言で自由に配分できるのは「正の財産」
- 「負の財産」を特定の人だけに引き継がせることは、原則として債権者に対抗できない
- ただし、債権者の同意があれば免責的債務引受契約で反映可能
6. まとめ
遺言書というと、どうしても「財産をどう分けるか」というプラス面に目が向きがちですが、負の財産の整理も同じくらい重要です。 債権者の権利を無視した遺言は効力を持ちません。負債がある場合には、債権者の意向を踏まえたうえで、家族と専門家を交えて慎重に内容を検討することが求められます。
なお、借金や保証債務に関する争いが予想される場合は、弁護士に相談することが最善の選択です。 行政書士としては、トラブル予防の観点から遺言内容や事前協議の段階でのご支援が可能です。
※本記事は現行民法(第896条〜第940条)および債権法の原則に基づき作成しています。
個別の契約内容・債権者対応については、弁護士・税理士など専門家にご相談ください。