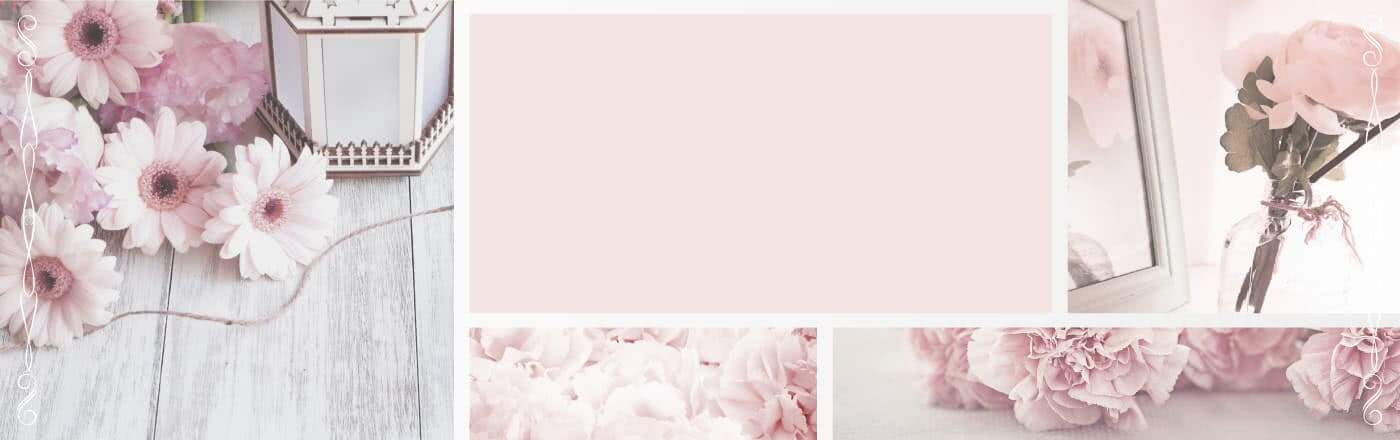「法律」「法令」「行政立法」「命令等」の違いをわかりやすく整理
行政書士試験の学習でも、実務でも混乱しやすいテーマのひとつが、「法律」「法令」「行政立法」「命令等」 といった用語の違いです。
私自身も伊藤塾の実務講座を受講して、改めて理解が深まりました。ここでは、これらの用語を丁寧に整理しながら、行政書士として押さえるべきポイントをまとめます。
1.「法律」とは何か
法律とは、国会が制定する最も基本的な法形式です。いわゆる「国会中心立法の原則」に従うものです。
一方、条例は地方議会が制定する法規で、国会中心立法の例外として位置付けられます。
つまり、法形式としては次のように整理されます。
- 法律:国会で制定される法規
- 条例:地方公共団体の議会が制定する法規(例外的立法)
2.「法令」とは何か(行政手続法の定義)
行政手続法では、「法令」を次のように定義しています。
- 法律
- 法律に基づく命令(=法規命令)
- 条例
- 地方公共団体の執行機関の規則(=行政規則)
つまり、法令という言葉には次の4つが含まれます。
- 国会が作る法律
- 法律に基づいて行政機関が作る法規命令
- 地方議会が作る条例
- 行政機関内部で作られる規則(行政規則)
この「幅広さ」が、法令という言葉を理解しづらくしている理由のひとつです。
3.行政立法(法規命令と行政規則)の分かりにくさ
行政立法は、次の2つに分類されます。
- 法規命令(国民に直接効力)
- 行政規則(行政内部のルール)
●条例で定める過料は「法規」としての性格
条例で過料を定めることは、国会中心立法の例外として「法規の一種」とされます。
●市長が科す過料は行政規則? それとも法規命令?
ここが受験生・実務家ともに最大の混乱ポイントです。
市長が科す過料は、
- 行政の内部規則として扱われる(行政規則)
- しかし、地方自治法を根拠に法規命令に基づいて科されるとも整理される
さらに、市長の科す過料は、
- 罰金ではない
- 行政刑罰にも当たらない
- 秩序罰として位置づけられる
という特殊な性質をもっています。
このように、行政規則でありながら、法規命令との接点もあるという点が、行政立法を理解しづらくしている要因です。
4.「命令等」とは何か(行政手続法の定義)
行政手続法における「命令等」は、次のように定義されています。
(1)命令等の範囲
- 法律に基づく命令(=法規命令/執行命令)
- 行政機関が定める規則(行政規則)
- 審査基準
- 処分基準
- 行政指導指針
(2)法規命令とは
国民の権利義務に直接影響を及ぼす行政立法であり、
- 施行令
- 施行規則
などが該当します。
(3)行政規則とは
行政規則とは、行政内部で用いられるルールであり、
- 裁量基準
- 行政指導指針
などが含まれます。
国民の権利義務には直接影響しない点が大きな特徴です。
5.行政法は「原則・例外・例外の例外」が多い世界
行政書士試験でも痛感しますが、行政法はとにかく「例外規定」が多く、理解したつもりでも混乱しがちな分野です。
特に行政立法の区分は、
- 法規命令と行政規則
- 条例と市長の過料
- 法律に基づく命令と行政内部の命令
など、似ている用語が多く、誤解を招きやすい部分です。
しかし、体系的に整理すれば確実に理解できますし、実務では大きな武器になります。
行政書士として、こうした「微妙な線引き」を丁寧に扱う姿勢が求められますね。