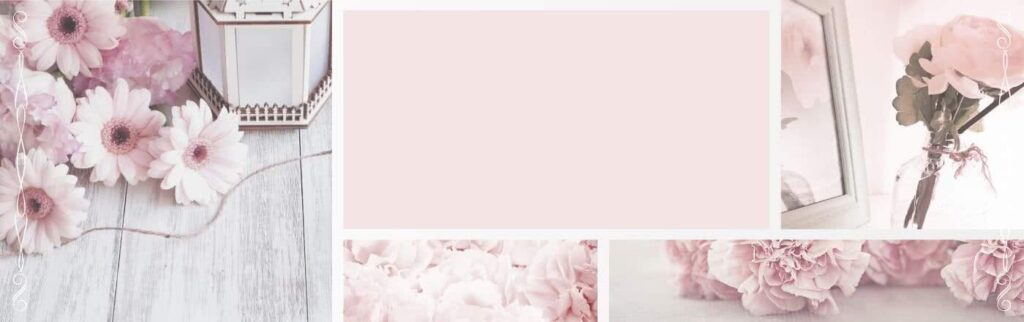このタイトルは、以前のブログ記事にも書いた論点ですが、もう少し分かりやすくまとめ直してみたいと思います。言いたくないから言わない。言いたいけど言えない場合が含まれるかどうかは別として、一般的にだんまり(黙秘)と沈黙が法的にどのような扱いになるかについて行政書士の視点で記述したいと思います。
民事訴訟において、当事者が口頭弁論で相手方の主張した事実について争う姿勢を示さない場合、その事実を「自白したものとみなす」とする規定が、民事訴訟法第159条第1項に定められています。
条文の概要
民事訴訟法第159条より抜粋
第159条(自白の擬制)
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
この条文は、訴訟の迅速化と争点整理を目的とした規定であり、沈黙が「不利な自白」として扱われる可能性がある点に注意が必要です。
「みなす」と「推定する」の違い
用語 意味 反証可能性
【みなす】法的に確定的な扱いをする(擬制) 原則として反証不可。
【推定する】 一定の事実から他の事実を推測する 反証により覆すことが可能。
つまり、「沈黙」は自白とみなされる(反証困難)一方、「知らない」と述べることで争う意思があると推定される(反証可能)という違いがあります。
実務上の注意点
民事の場合、被告が沈黙した場合、原告の主張がそのまま認定されるリスクがあります。
「知らない」と述べるだけでも争う意思があると推定され、擬制自白を回避できます。
ただし、弁論全体の趣旨から争っていると認められる場合は、擬制自白は適用されないということになります。
このように、民事訴訟では沈黙が不利に働く可能性があるため、争う意思がある場合は明確に表明することが重要です。
刑事訴訟法311条との比較:黙秘権の保障
一方、刑事訴訟法第311条では、被告人に対して「終始沈黙する権利」や「供述拒否権」が明確に保障されています。
条文の概要
刑事訴訟法第311条 抜粋
第311条
1 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
この規定は、憲法第38条の「自己に不利益な供述を強要されない」権利を具体化したものであり、民事訴訟法159条とは根本的に異なる趣旨を持つと考えられています。
民事と刑事の沈黙の違い
分類 沈黙の効果 根拠法 備考
民事訴訟 自白とみなされる可能性あり 民事訴訟法159条 争う意思を示さないと不利。
刑事訴訟 黙秘権として保障される 刑事訴訟法311条、憲法38条 沈黙しても不利益に扱われません。(原則)
刑事訴訟では、沈黙が権利として認められており、これを理由に不利な推認をすることは許されません。以上が、民事と刑事の大きな差ということになります。
行政書士の業務範囲と民事訴訟法の学習意義
行政書士は、民事訴訟に関する代理や助言を行うことは法律上認められていません(弁護士法第72条)。ただし、行政不服審査法に基づく不服申立てに関しては、特定行政書士として代理業務が可能です。
行政不服審査法との関連性
行政不服審査法では、審理手続において「口頭意見陳述」や「主張の整理」が行われるなど、民事訴訟法の弁論手続と類似する部分があります。
類似点 民事訴訟法 行政不服審査法
主張整理 弁論準備手続 審理員による整理
意見陳述 口頭弁論 口頭意見陳述(第29条)
争点明確化 要件事実の認否 審査請求の理由の検討
このため、行政書士試験では民事訴訟法の基本的な理解が求められ、特に「擬制自白」や「推定」の概念は頻出論点となっています。また、特定行政書士の修了試験などにおいても論点となっています。
まとめ
民事訴訟法159条では、沈黙が「自白」とみなされる可能性があるため、争う意思は明確に示す必要があります。
「知らない」と述べることで争う意思が推定され、擬制自白を回避できるからです。
刑事訴訟法311条では、黙秘権が保障されており、沈黙が不利益に扱われることはありません。
行政書士は民事訴訟の代理はできないが、行政不服審査法における審理手続との類似性から、民事訴訟法の理解は試験・実務において重要です。
このような視点から、民事訴訟法159条の理解は、行政書士試験対策のみならず、行政手続の適正な運用にも役立つ知識となります。
行政書士中川まさあき事務所(福井県越前市)