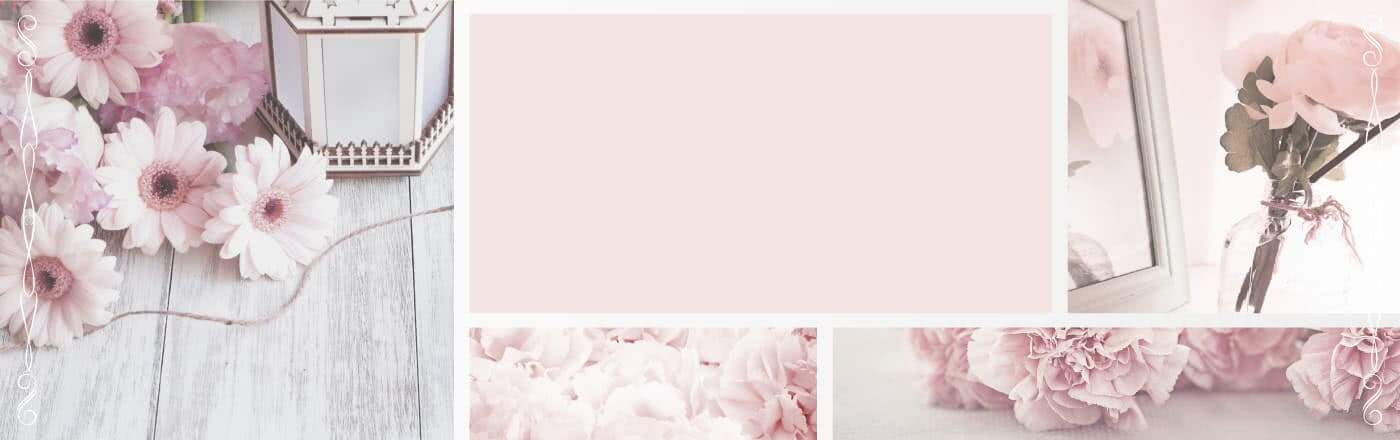【特定行政書士試験対策】民事訴訟における弁論主義の3つの柱と職権探知主義との違いを整理しよう
特定行政書士を目指して勉強を進めていると、民事訴訟法の「弁論主義」という概念が頻繁に登場します。この考え方は、裁判所がどのような立場で事実認定や証拠調べを行うべきかという基本的なスタンスを示す重要な原則です。この記事では、弁論主義の三つの基本原則(テーゼ)を明確に整理し、それと対比される「職権探知主義」との違いについても学びます。
弁論主義とは?裁判所の中立的立場を保つ原則
弁論主義とは、民事訴訟において裁判所が当事者の主張・立証に依拠して判断を下すべきという原則です。裁判所が独自に事実や証拠を探すのではなく、あくまで当事者が提供する情報に基づいて審理・判決を行うというスタンスです。
この弁論主義には、次の3つの柱(テーゼ)があります。
第1テーゼ:主要事実は当事者が主張しなければならない
裁判所は、当事者が主張しない事実(=主要事実)を判決の根拠としてはいけません。つまり、争点の形成は当事者の主張によって行われ、裁判所が職権で補完することは原則として認められていません。
第2テーゼ:自白された事実はそのまま認定される
当事者の一方が他方の主張を争わず、自白した場合には、その事実は争いのないものとされ、裁判所は証拠調べをせずにそのまま事実として採用しなければなりません。
第3テーゼ:証拠は当事者が提出したものに限られる
裁判所が争いのある事実について証拠に基づいて認定する場合、使用できる証拠は当事者が申し出たものに限られます。裁判所が自ら証拠を収集・調査すること(職権証拠調べ)は禁止されています。
職権探知主義との違いとは?
弁論主義とは対照的に、裁判所や審査機関が自ら資料収集や証拠調べを行う「職権探知主義」という考え方もあります。以下は各法分野ごとの対応です。
| 法律 | 職権証拠調べ | 職権探知 |
|---|---|---|
| 民事訴訟法 | × | × |
| 人事訴訟法(例:離婚) | ◯(第20条) | ◯ |
| 行政事件訴訟法 | ◯(第27条) | × |
| 行政不服審査法 | ◯ | ◯ |
理解のポイント:「誰が」「誰に」「何を」「どうする」
学習を進める上で大切なのは、「主語」を明確にして制度の構造を理解することです。
- 誰が:裁判所か審査庁か
- 誰に:当事者か申立人か
- 何を:事実の主張・証拠提出・調査の権限
- どうする:申出に基づいて行うのか、職権で行うのか
- 結果:どのような判断が導かれるか
このようなフレームで整理しておくと、試験問題で問われた際にも混乱しにくくなります。
まとめ
弁論主義の三つのテーゼは、民事訴訟の基本的な枠組みを理解するうえで非常に重要な論点です。そして、職権探知主義との違いを比較しながら学ぶことで、特定行政書士として必要な法的理解が一層深まります。制度の根拠や適用範囲、主体の違いをしっかり整理し、確実な知識として定着させましょう。