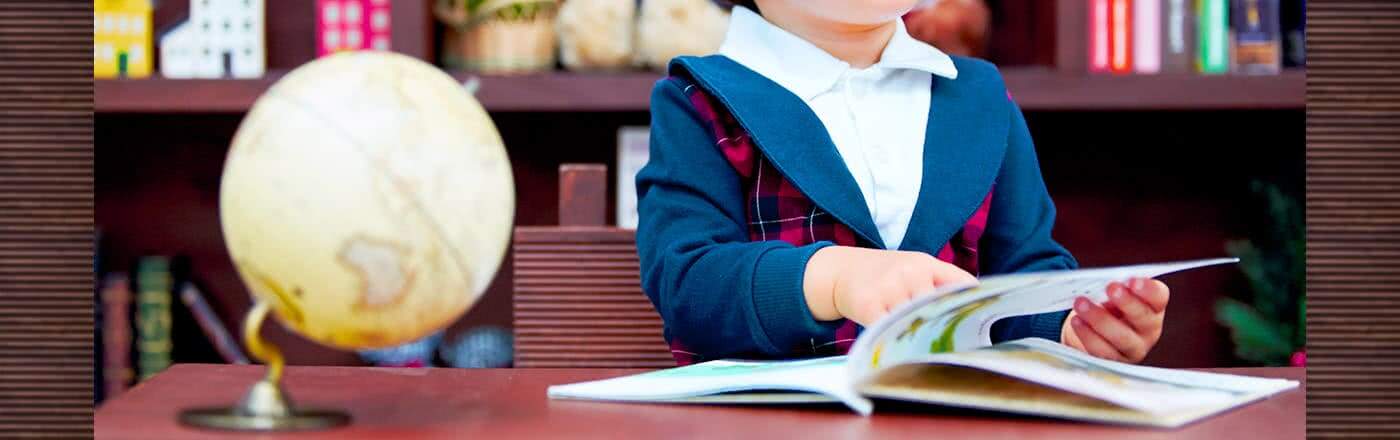身内が亡くなったときにまず読む相続手続きガイド|行政書士がやさしく解説
身内が亡くなったとき、まず何をすればいい?
— 身近な行政書士が窓口となる「相続手続き」の第一歩 —
突然のご不幸に直面すると、何から手を付けるべきか判断が難しいものです。相続には期限のある手続きもあるため、迷ったらまずは身近な行政書士に相談するのが安心です。
本記事の構成
- 行政書士が相続で果たす役割
- 最初に確認すること:遺言書の有無
- 公正証書遺言とは
- 相続方法の選択(3か月以内)
- 相続人の確定と財産目録
- 遺産分割協議とその後の手続き
- 行政書士に相談するメリット
- よくある質問
行政書士が相続で果たす役割
行政書士法 第1条の2(要旨):行政書士は、報酬を得て、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類(図面類を含む)を作成することを業とします。ただし、他の法律で制限されている業務は行えません。
この定義に基づき、行政書士は相続において戸籍収集・財産調査・相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書等の作成を中心に、手続き全体を整理しながら進行管理を担います。
他士業との連携
- 司法書士:不動産の相続登記(行政書士は登記の受任不可)
- 税理士:相続税の相談・申告(行政書士は税務申告の受任不可)
- 弁護士:遺産分割の紛争・もめ事がある場合
行政書士が窓口になるメリット
- 初動整理(必要書類・期限・全体像)を一元化
- 各専門家への橋渡し・進行管理までワンストップ
- 感情面に配慮しつつ実務を淡々と前進
最初に確認すること:遺言書の有無
相続の第一歩は遺言書の存在確認です。考えられる保管先は次の3つです。
- 自筆証書遺言:自宅・金庫等に保管されている場合
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度:法務局に預けた場合は保管通知で把握可能
- 公正証書遺言:公証人役場に保管(通常、役場からの自動通知はありません)
検認手続きの要否
自宅保管の自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要。一方、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が遺言者の真意を確認し、証人2名の立会いのもとで作成する信頼性の高い方式です。内容の明確性・保存性に優れ、後日の紛争予防に役立ちます。
- 作成過程で公証人から助言を受けられる
- 原本は公証人役場で保管される
- 費用は政令で基準があり、相談は無料
相続方法の選択(3か月以内)
民法第915条により、相続人は「相続開始を知った日」から3か月以内に、次のいずれかを選びます。
- 単純承認:財産も負債もすべて承継
- 相続放棄:財産・負債を一切承継しない
- 限定承認:相続財産の範囲内でのみ負債を弁済(超過分は負わない)
限定承認の重要注意点
限定承認は有効な選択肢ですが、家庭裁判所への申立て、相続財産目録の作成、官報公告、債権者対応、準確定申告・譲渡所得課税の検討など、費用と手間、時間がかかります。実務負担が大きいため、専門家への早期相談が推奨されます。
相続人の確定と財産目録の作成
- 戸籍収集:出生から死亡までの連続した戸籍で法定相続人を確定
- 財産調査:預貯金・有価証券・投信・生命保険・自動車・不動産・債権・負債等を洗い出し
- 図・目録作成:相続関係説明図・財産目録を整備
※未登記不動産や先代名義のままの物件が見つかると、整理に時間を要する場合があります。
遺産分割協議とその後の手続き
遺言書がない場合は、相続人全員で配分を話し合い、遺産分割協議書にまとめます(署名・実印)。
その後、銀行・証券会社・生命保険・自動車・不動産登記など、各機関で名義変更・移管・相続登記を進めます。
- 手続きの多くは専門家への委任が可能(委任状が必要な場合あり)
- 不動産売却による換価分配は、遺言執行者が単独で手続きできるケースあり
- 農地・土地改良区・各種資格・許認可・会社役員の変更等、個別の届出が必要な場合あり
- 相続税の申告・納税は、原則相続開始を知った日の翌日から10か月以内(税理士と連携)
行政書士に相談するメリット
- 初動で全体像を整理(必要書類・期限・関係者)
- 戸籍収集〜協議書作成まで一括支援
- 司法書士・税理士・弁護士等と連携しワンストップで対応
- ご家族の気持ちに寄り添い、粘り強く進行管理
小さな不安でも構いません。まずは状況をお聞かせください。
相続の負担を最小化し、期限を逃さず、誤りのない手続きへ導きます。
よくある質問
まず何から始めればよいですか?
死亡届・葬儀と並行し、遺言書の有無確認と相続方法(単純承認/相続放棄/限定承認)の検討を開始します。期限があるため、早めの専門家相談をおすすめします。 限定承認はどんなときに選ぶべき?(費用・手間・時間は?)
負債額が不明なときの選択肢です。ただし、裁判所申立て・目録作成・公告・債権者対応等が必要で、費用と手間、時間がかかります。ケースにより負担は異なるため、実務経験のある専門家に試算・段取りを相談しましょう。 遺言書が見つかった場合の手続きは?
自宅保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。内容に従い、遺言執行者(専門家が指名されることも多い)が執行します。 紛争になりそうです。どこに相談すべき?
遺産分割で揉めている・揉めそうな場合は弁護士への相談が適切です。行政書士は手続き整理・書類作成・他士業連携の窓口として支援します。
※本記事は一般的な解説です。個別事情により最適解は異なります。
不動産登記は司法書士、税務申告は税理士、紛争案件は弁護士の管轄です。行政書士はこれらの受任はできませんが、総合窓口として連携し、円滑な手続きをサポートします。