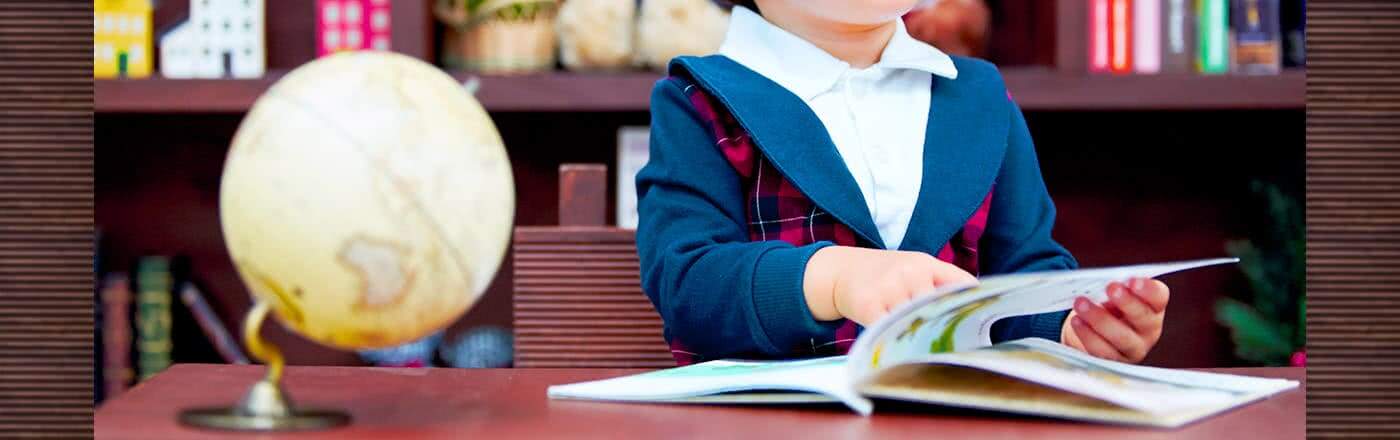【相続の「子」視点】実子・非嫡出子・養子・連れ子…6パターン整理と勘違いしやすい4論点を行政書士が解説
【相続の「子」視点】6パターンの整理と、勘違いしやすい4つの論点
— 条文と公的情報に基づくやさしい実務解説(福井の行政書士・中川正明) —
はじめに:この記事のねらい
相続関係を「子(こ)」の立場から考えるとき、誰が相続人に当たるのか、相続分は同等か1/2か、代襲相続(だいしゅうそうぞく)はどこまで及ぶか、そしていつまでに何をすべきかが混同されがちです。本記事は、次の6パターンを土台に、法務省・e-Gov・国税庁など公的情報に基づいて整理します。必要に応じて一次情報へのリンクも添えました。
「子」に関する6パターン(前提)
- ① 被相続人の子(実子)
- ② 離婚した元配偶者との間の子(実子)
- ③ 婚姻関係にない者との間の子(非嫡出子/実子)
- ④ 被相続人の「子」が養子で、その養子の配偶者の連れ子
- ⑤ 被相続人の「子」が養子で、その養子の配偶者との間に養子縁組後に生まれた子
- ⑥ 被相続人の「子」が養子で、その養子の配偶者との間に養子縁組前に生まれた子
論点① 被相続人から見る関係で整理する(混乱防止のコツ)
相続人の判断は、「相続される側=被相続人」から見た関係で整理すると迷いにくくなります。
- ④ 連れ子(子の配偶者の連れ子)は、被相続人と血縁がないため相続人ではありません(養子縁組しない限り)。
→ ただし、被相続人の「子(=養子)」とその連れ子が養子縁組をしただけでは、被相続人と連れ子の間に直系の関係は生じません。被相続人と連れ子の間に法的な親子関係を作るには、被相続人自身が連れ子と養子縁組をする必要があります(民法727、趣旨)。 - ⑤ 養子縁組後に生まれた養子の子は、被相続人にとって法定血族としての直系卑属(=孫)に当たり、一定要件で代襲相続が可能です(民法727、887条2項ただし書の解釈)。
- ⑥ 養子縁組前に生まれた養子の子は、被相続人の直系卑属に当たらないため、代襲相続になりません(民法727の効果が縁組日以降に及ぶため)。
参考:民法(e-Gov)/縁組の効果(民法727条の解説)/実務解説例:養子の子の代襲相続の可否。
論点② 相続分は「同等」か「1/2」か(非嫡出子と兄弟姉妹を混同しない)
(A)実子と非嫡出子の相続分は同等
かつて民法900条4号ただし書にあった「非嫡出子は嫡出子の1/2」という規定は、最高裁平成25年9月4日大法廷決定により違憲と判断され、立法改正で削除されました。以後、実子と非嫡出子は相続分が同等です。
参考:法務省:民法の一部改正(非嫡出子相続分)/判例解説例(概要)こちら。
(B)兄弟姉妹(半血/異父母兄弟姉妹)の相続分は1/2
一方で、被相続人の兄弟姉妹同士では、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血/異父母兄弟姉妹)の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の1/2です(現行民法900条4号括弧書)。
参考:民法900条(法定相続分の規定)
ポイント
「実子 vs 非嫡出子」は同等。
「全血兄弟姉妹 vs 半血兄弟姉妹」は1/2。
— 対象(子か兄弟姉妹か)を混同しないことがコツです。
論点③ 代襲相続・再代襲はどこまで及ぶ?
| 系統 | 代襲の可否 | 根拠の考え方 |
|---|---|---|
| 直系卑属(子→孫→曾孫) | 代襲・再代襲ともあり | 民法887条(子の子による代襲、孫の子による再代襲) |
| 兄弟姉妹 | 代襲あり/再代襲なし | 民法889条2項(再代襲は準用なし) |
※ 昭和23年1月1日〜昭和55年12月31日に開始した相続には旧法が関係し、兄弟姉妹でも再代襲が認められた時期があります。個別にご確認ください。
参考:代襲・再代襲の実務解説(弁護士解説)
論点④ 「いつまで?」主要な期限・時効まとめ
- 相続放棄・限定承認:相続開始を知った日から原則3か月以内(民法915条)。e-Gov
- 死後認知の訴え:父母の死亡から3年以内(民法787条)。e-Gov
- 相続税の申告・納付:相続開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税法)。国税庁
- 相続回復請求権:侵害を知って5年、または相続開始から20年(民法884条)。e-Gov
- 特別受益・寄与分の主張:原則、相続開始から10年以内(令和5年4月1日施行の改正)。※10年経過後は法定相続分が原則となり、具体的相続分(特別受益・寄与分)を主張できません(例外あり)。
参考:解説コラム/税理士解説
税務の実務的注意(養子の人数制限)
相続税の計算上「法定相続人の数」に含められる養子の人数は、実子あり=1人まで/実子なし=2人までです。相続権そのものの有無とは別の「税法上のカウント」ですので混同に注意(国税庁タックスアンサーNo.4170)。
Q&Aで補足(よくある誤解)
Q1. 兄弟姉妹には遺留分はありますか?
いいえ。兄弟姉妹に遺留分はありません。したがって、兄弟姉妹を排除したい場合は、遺言で「相続させない」旨を明記すれば足ります(遺留分侵害額請求の対象外)。
Q2. 廃除(民法892条)・欠格(民法891条)と代襲相続の関係は?
欠格も廃除も本人の相続権は失われますが、原則としてその子や孫には代襲相続が認められます(民法887条2項)。
参考:条文リンク(民法891・892)
Q3. 養子の「子」は、いつ代襲できますか?
養子縁組後に生まれた子(胎児で縁組後出生を含む)は、被相続人(養親)の直系卑属にあたり代襲可能。一方、縁組前に生まれた子は代襲できません(民法727、887条2項の解釈)。
まとめ:条文ベースで「整理」→「準備」へ
- 誰が相続人かは被相続人から見た関係で判断。
- 「子」と「兄弟姉妹」の相続分ルールは別物(非嫡出子は同等/半血は1/2)。
- 代襲相続は直系は再代襲まで可、兄弟姉妹は1代限り。
- 「3か月」「10年」「5年・20年」など期限の管理が実務の肝。
相続は感情の対立を招きやすいテーマです。紛争化のおそれがある案件は弁護士の領域ですが、紛争にならないように備える予防法務(遺言書作成、関係図・一覧図の整備、期限管理)は行政書士の腕の見せどころ。福井エリアでの相続・遺言のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。
公的リンク(一次情報)
- 民法(e-Gov 法令検索):相続・親族編の条文(891欠格/892廃除/887・889代襲/900相続分/915期間 ほか)
- 法務省:非嫡出子相続分に関する改正/相続登記義務化Q&A
- 国税庁:No.4170 養子を含める人数の制限/No.4102 相続税がかかる場合
執筆・監修:中川正明(特定行政書士/申請取次行政書士/宅地建物取引士)|福井県越前市
※本記事は法務省・e-Gov・国税庁等の公的情報を参照して作成しています。個別の事情により結論が変わる場合がありますので、最新の一次情報の確認と専門家へのご相談をおすすめします。