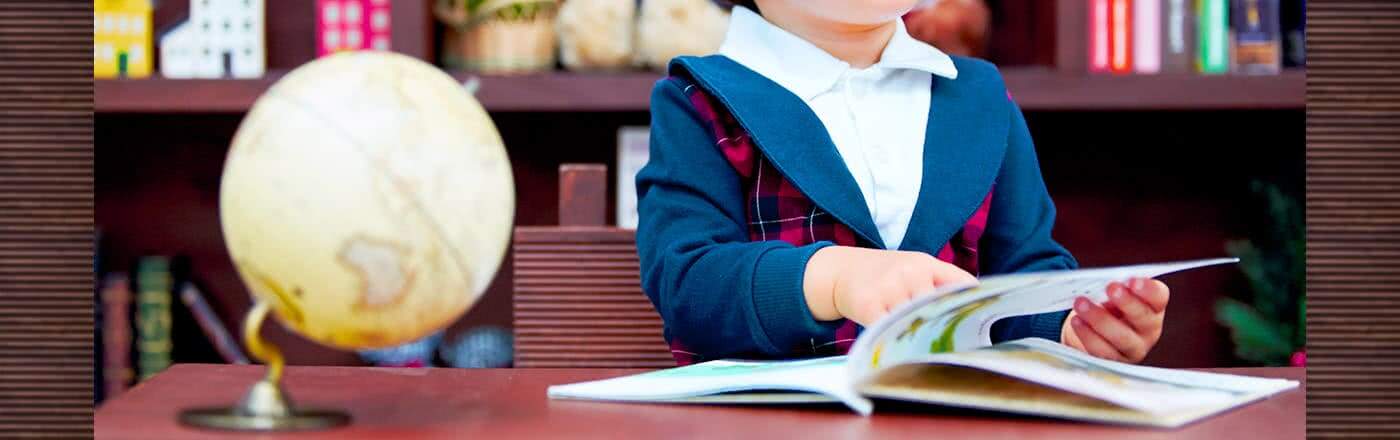相続で必要な戸籍謄本とは?種類・違い・取得方法を行政書士が解説
相続が発生すると、被相続人や相続人の関係を明確にするために「戸籍謄本一式」を収集します。 戸籍謄本といっても、実際には複数の種類があり、それぞれ役割や取得先が異なります。 本記事では、相続で必要となる各種戸籍の種類と違い、そして最新の取得制度(令和6年3月施行の広域交付制度)までを、行政書士の立場からわかりやすく整理します。
1. 「戸籍謄本」とは何か?相続で必要な理由
戸籍謄本は、家族関係(親子・配偶者など)を証明する最も基本的な書類です。 相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡までのすべての戸籍を遡って取得し、相続人を確定するために使われます。
ポイント: 被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍を収集しなければ、正確な相続人の確定はできません。
2. 戸籍謄本と戸籍抄本の違い
- 戸籍謄本:同じ戸籍に記載されている全員の情報を証明するもの
- 戸籍抄本:その戸籍の中の特定の1名分のみを証明するもの
なお、現在の制度では「戸籍謄本=戸籍の全部事項証明書」、「戸籍抄本=戸籍の個人事項証明書」という名称で発行されています。
3. 戸籍の一部事項証明とは
戸籍の中の特定の事実(例:婚姻、死亡、離婚など)だけを証明する書類です。 こちらは本籍地の自治体でのみ発行可能で、証明内容が限定されるため、相続関係の証明としては補助的に使われます。
4. 除籍謄本と除籍抄本
除籍とは、その戸籍に記載されていた全員が転籍・死亡・婚姻などで除かれた状態を指します。 そのため、除籍謄本は「過去にその戸籍に在籍していた全員の記録」を証明するものです。
- 除籍謄本:除籍となった戸籍全員分を証明
- 除籍抄本:除籍された中の1名分を証明
相続では、被相続人が過去にどの戸籍に属していたかを確認するため、除籍謄本は必ず取得することになります。
5. 改製原戸籍とは(旧様式の戸籍)
法令やシステム改正により戸籍様式が変わることを「改製」と呼びます。 その改製前の古い戸籍を「改製原戸籍」といいます。
改製原戸籍は、昭和・平成初期などの古い記録をたどる際に必要であり、被相続人の出生や親子関係を確認するために欠かせません。 多くの場合、除籍謄本のさらに一つ前に遡る形で取得します。
6. 戸籍の附票と住民票の除票の違い
被相続人の「最後の住所地」や住所履歴を確認する際に使うのがこれらの書類です。
- 戸籍の附票:戸籍に紐づく住所履歴。すべての転居履歴が記載される。
- 住民票の除票:転出・死亡等により住民票が除かれた際に発行。前住所は記載されるが、履歴は一部のみ。
戸籍の附票には「全部証明」と「一部証明」があります。
相続では被相続人の住所履歴を特定するため、「全部証明」を請求するのが一般的です。
7. 広域交付制度のスタート(令和6年3月1日施行)
これまで戸籍関係書類は本籍地の市町村でしか取得できませんでしたが、令和6年3月からは、全国どこの市町村窓口でも交付請求が可能になりました(本人・法定代理人・委任状による請求に限る)。
ただし、マイナンバーカードを使った本人確認や、請求理由の確認が必要になるため、事前に自治体や法務局の案内を確認することが大切です。
戸籍収集は相続の最初のステップであり、誤りや漏れがあると遺産分割や登記手続きが進まなくなります。
行政書士中川まさあき事務所では、戸籍・除籍・改製原戸籍・附票の収集代行から相続関係説明図の作成まで、安心してお任せいただけます。
※本記事は、令和6年3月施行の広域交付制度および現行の戸籍法に基づいて作成しています。
詳細は法務省・自治体の公式ホームページをご確認ください。