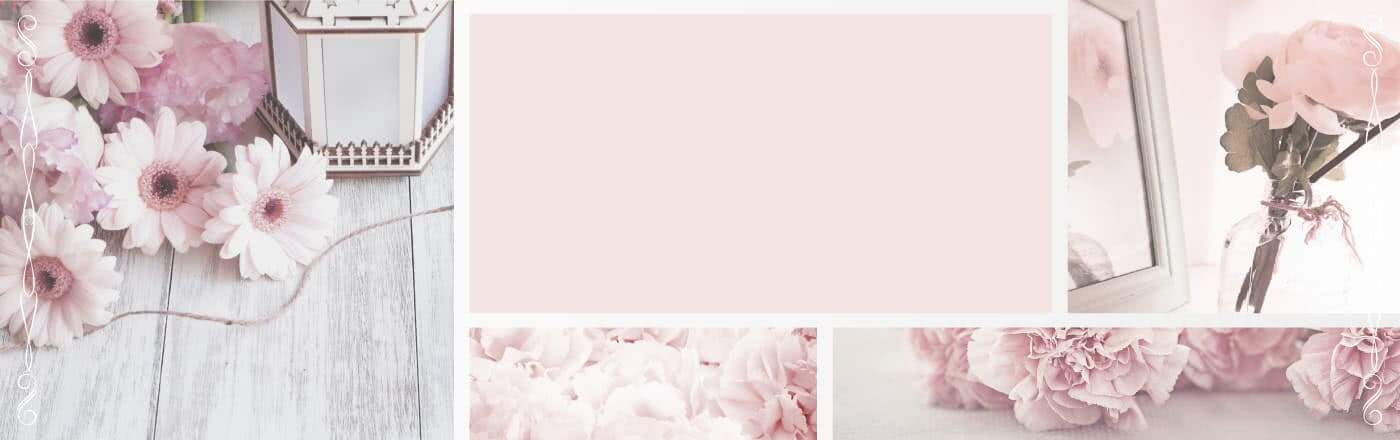要件事実とは?特定行政書士試験対策に効く「攻撃防御構図」の整理
特定行政書士試験の実務論点として、民事訴訟構造の「要件事実」論は必須です。特に、
- 原告側が主張すべき「請求原因」
- 被告側が主張すべき「抗弁」
という攻防構図を理解しておくことが、書面作成や手続対応の場面でも役立ちます。この記事では、要件事実を法律効果に沿って4分類し、さらにその図示手法「ブロック・ダイヤグラム」も紹介。さらに、行政不服審査請求の代理業務を行う立場から、これら知識をどう活用できるかも述べます。
1.要件事実を4つに分類する理由
民事訴訟において、裁判所が適用すべき実体法(例えば 民法)の規定には、法律効果の発生・障害・消滅・阻止といった四つの局面があります。これを、訴訟の主張・立証という観点から整理すると、以下のような分類が可能です。
| 分類番号 | 名称(概念) | 内容 | 典型例 |
|---|---|---|---|
| ① | 権利根拠事実(請求原因) | 原告が主張すべき「この権利が発生しました」という事実 | 売買契約の成立、貸金の貸付契約の成立等 |
| ② | 権利障害事実(抗弁) | 被告が「権利が発生しない」と主張する事実 | 錯誤・無効・取消の主張など |
| ③ | 権利消滅事実(抗弁) | 被告が「権利は既に消滅している」と主張する事実 | 弁済・相殺・消滅時効など |
| ④ | 権利阻止事実(抗弁) | 被告が「権利行使を阻止する」と主張する事実 | 同時履行の抗弁、催告の抗弁など |
2.原告・被告の主張構図と「認否」の種類
原告の主張
原告は、自身の主張する権利根拠(①)を訴状等で主張・立証し、裁判所に「この請求を認めてください」という構成を取ります。
被告の反論(抗弁)
被告は、原告の主張を認めるか否かをまず「認否」によって答えたうえで、抗弁(②~④)を主張・立証していきます。認否の典型的な類型は以下の通りです。
- 自白: 原告の主張する事実を認める
- 否認: 主張する事実を争う
- 不知: 事実の有無を知らない・確認できない
- 沈黙: 応答をしない(実務上はほぼ使われません)
抗弁は、請求原因(①)と両立する事実を根拠とし、その法律効果を「妨げる/消滅させる/阻止する」ものとして機能します。
3.「ブロック・ダイヤグラム」で可視化する
要件事実論を図式的に整理するために、司法研修所などでは「ブロック・ダイヤグラム」という手法が紹介されています。
これは以下のように主張構造を視覚的に整理します:
- 原告の主張(①)
- 被告の抗弁(②/③/④)
- 再抗弁・再々抗弁 …
構図を視覚化することで、「誰が何を主張すべきか」が明確になり、書面作成の実務にも役立ちます。
4.行政不服審査請求と要件事実の関係
行政不服審査法における審査請求も、民事訴訟と同様に「誰が、どのような理由で、何を求めるのか」という構造を意識する必要があります。
特定行政書士として代理人業務にあたる際には、
- 請求人がどのような根拠事実に基づいて処分取消等を求めるか
- 行政庁側がどのような抗弁的主張をする可能性があるか
といった点を事前に整理しておくことで、効果的な主張構成が可能になります。
5.まとめ:特定行政書士として知っておくべきポイント
- 要件事実は①〜④の4分類で整理することで、主張構造が明確になる
- 原告は①を、被告は②〜④を主張・立証する
- 「認否」と「抗弁」の違いを理解することが重要
- 「ブロック・ダイヤグラム」を活用すれば、論点整理が視覚的に把握しやすくなる
- 審査請求にも同様の構造を応用でき、書面作成に有用
このような知識を確実に押さえておけば、特定行政書士として代理書面や準備対応時に、自信を持って主張・反論の整理ができるようになります。ぜひ、書面作成演習や過去問分析とあわせて、要件事実の構造を自身のものにしてください。